この記事でわかること
- 見積書が電子帳簿保存法の保存対象となる理由と法的根拠
- 電子取引・紙書類の受領パターン別、保存方法の違い
- タイムスタンプや検索機能など、保存要件として満たすべきポイント
- 契約に至らない見積書やメール本文などの扱いに関する実務上の留意点
- 見積書保存に関するよくある質問と回答
2024年1月から電子取引の保存義務が原則化され、見積書の保存方法にも大きな影響が及んでいます。メールやWebで受け取った見積書も、電子帳簿保存法に則った形で保存しなければなりません。保存期間や形式、要件を満たさない場合はコンプライアンス上のリスクとなるため、正しい知識と対応が必要です。本記事では、電子帳簿保存法における見積書の位置づけと、適切な保存方法・注意点を具体的に解説します。
見積書は電子帳簿保存法の対象書類

見積書は、税務処理や会計上の根拠資料として重要な帳票であり、電子帳簿保存法でも保存対象に含まれます。特に、メール添付やクラウドサービスで授受された見積書は「電子取引」に該当し、法令で定められた電子保存の要件を満たす必要があります。ここでは、見積書が電子帳簿保存法の対象となる法的根拠と、保存義務の範囲・条件を解説します。
見積書の保存義務が発生する条件
見積書が電子帳簿保存法において保存義務の対象となるかは、「電子取引」に該当するかどうかが基準となります。電子取引とは、取引情報を電磁的記録で授受することを指し、たとえば次のような場合が該当します。
- 見積書をPDFでメール送付した場合
- クラウドサービス経由で送受信した場合
- Webフォームなどのシステム経由でやり取りした場合
上記に該当する場合、見積書は「電子取引データ」とみなされ、紙に印刷して保存するだけでは法令違反となります。原則として電子データのまま、電子帳簿保存法に準拠した方法で保存する必要があります。
一方、FAXや郵送など紙媒体で授受された場合は電子取引に該当せず、従来通り紙保存も可能です。ただし紙をスキャナ保存に切り替える場合は、別途定められた要件を満たす必要があります。
見積書の法定保存期間
見積書は法人税法や所得税法における「取引関係書類」として位置づけられ、保存期間が法令で定められています。具体的には、法人は7年間、個人事業主は5年間の保存が原則です。ただし、青色申告で欠損金が発生している場合など、保存期間が10年に延長されることもあります。
保存期間の起算点は、見積書に基づいて契約や取引が成立した日、あるいは決算日の属する事業年度の確定申告書の提出日などが基準となります。取引が成立しなかった場合でも、見積書が「確定データ」とみなされる場合は保存対象になるため、安易な破棄は避けるべきです。
また、見積書は後日の税務調査などで参照される可能性もあるため、関連する契約書・請求書などとあわせて一元管理するのが望ましいでしょう。
受領した見積書をデータ保存する場合の保存方法

見積書をデータで保存する方法は、受領方法によって異なります。電子メールやWebシステムなどで受け取った場合は「電子取引」として電子保存が義務付けられ、要件を満たした形式で保存しなければなりません。一方、紙で受領した場合は「スキャナ保存」によりデータ化できますが、一定の技術的・運用上の要件を満たす必要があります。
電子データで受領(電子取引)した場合
・電子帳簿保存法に準拠した「電子保存」が必須
・タイムスタンプや検索機能、真実性の確保が必要
紙で受領した場合
・原則は紙保存
・電子保存に切り替えるには「スキャナ保存」の要件を満たす必要あり
・解像度や保存時期、訂正削除の記録保持が必須
電子取引の保存
メールやクラウドサービス経由で見積書を受領する行為は「電子取引」に該当し、電子帳簿保存法に基づきデータのままで保存することが義務付けられています。保存にあたっては、以下のとおり「真実性」と「可視性」の要件を満たす必要があります。
真実性の要件(次のいずれか1つ)
- タイムスタンプが付された後に受領
- 受領後、速やかにタイムスタンプを付与
- 訂正・削除の履歴が残る、または不可能なシステムを使用
- 訂正・削除防止のための事務処理規程を備え付ける
可視性の要件(すべて必要)
- システム概要書の備付け(自社開発システム利用時)
- 見読可能な装置(ディスプレイ・プリンタ等)の備付け
- 検索機能の確保
①取引年月日、金額、取引先で検索可能
②日付または金額の範囲指定による検索が可能
③複数項目を組み合わせた検索が可能(②③は任意条件あり)
※税務職員によるダウンロード要請に応じられる場合、小規模事業者は②③や検索機能自体を省略可。
発行側も同様の保存要件を満たす必要があり、送信履歴だけでなく、見積書ファイルそのものを保存することが必要です。
参考:国税庁 「電子取引データの保存」
紙からのスキャン
紙で受領した見積書を電子データとして保存する場合、「スキャナ保存制度」を活用することで、原本を破棄し電子データのみでの保存が可能となります。ただし、そのためには電子帳簿保存法で定められた要件を満たす必要があります。
真実性の確保(いずれか)
- 適時入力(最長で概ね7営業日以内)
- タイムスタンプの付与
- 訂正・削除履歴の保持(バージョン管理)
- 入力責任者・手順などを定めた事務処理規程の備付け
スキャンの技術要件
- 解像度:200dpi以上で読み取り
- 階調:白黒階調でも可(カラーは各色256階調以上推奨)
- ファイル形式:PDFやTIFFなど、改ざんが困難な形式推奨
可視性・検索性の確保
- 14インチ以上の画面で4ポイント文字が認識可能な装置
- 検索機能(取引年月日・金額・取引先名などで検索可能)
- システム概要書や運用手順書の備付け(特に自社開発時)
なお、スキャナ保存を行うか紙で保管するかは企業側の判断に委ねられていますが、検索性の向上や保管スペースの削減などの点から、スキャナ保存の導入は実務上も有効な選択肢です。
参考:国税庁 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】(令和2年6月)
受領した見積書のデータ保存で注意すべきポイント

電子帳簿保存法に基づいて見積書を電子保存する際は、真実性・可視性・検索性の3要件を満たすことが求められます。中でも、下記は実務上の重要なポイントです。
・タイムスタンプの付与
・検索機能の確保
タイムスタンプ
タイムスタンプは、電子データが改ざんされていないことを証明する手段として、電子帳簿保存法において重要な役割を担っています。電子取引やスキャナ保存においては、以下のいずれかの方法で「真実性の確保」を実現する必要があります。
タイムスタンプの付与期限
- 受領から最長2か月+7営業日以内に付与
- スキャナ保存では、入力期間内に保存した事実が確認できる場合、タイムスタンプの代替可
代替手段として認められる方法
- 訂正削除履歴を管理できるシステムでの保存
- 訂正削除の防止に関する事務処理規程を定め、備え付け・運用する方法
受領方法によっても対応は異なり、PDFやクラウドで受け取る場合は、上記のいずれかの方法で保存が必要です。クラウドサービス上に一時保存したデータをローカルへダウンロードして保存する場合も、同様の対応が求められるため注意が必要です。
検索機能
電子帳簿保存法では、スキャナ保存・電子取引のいずれの場合も、保存データに対して適切な検索機能を確保することが必要です。税務調査時に迅速なデータ提示が可能となるため、以下の3項目すべてを満たすことが原則です。
検索機能の要件(通常要件)
- 取引等の「日付・金額・取引先」による検索が可能であること
- 「日付」または「金額」について範囲指定で検索できること
- 「日付・金額・取引先」を組み合わせた検索ができること
ただし、税務職員からの求めに応じて保存データを一括ダウンロードで提供できる体制がある場合には、②と③の要件は免除されるとされています。小規模事業者などにおいては、これを活用することで検索要件の簡素化が可能です。
見積書は必ずしも帳簿と紐付ける必要はありませんが、帳簿と一致する金額や取引先名などで検索できるように管理しておくことで、法的要件を満たすと考えられます。
見積書のデータ保存に関する電子帳簿保存法上の留意点

見積書の保存においては、契約の有無や発行形態に関わらず、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。特に次のような点は実務上よく問われるため、注意が必要です。
・契約に至らない場合の扱い
・メール本文の保存範囲
・見積書を複数受領時の対応
契約に至らない場合の扱い
電子帳簿保存法には、「契約に至らなかった見積書の保存」について明確な規定はありません。しかし、見積書が電子取引に該当する形で授受されたものであれば、契約の成否にかかわらず電子保存の対象となる可能性があるため、保存しておくことが望ましいとされています。とくに次のような理由から、契約に至らなかった見積書も保存するメリットがあります。
- 将来的に同様の取引があった際に、参考資料として活用できる
- 電子保存しておけば検索性が高く、保管スペースも不要
また、税務調査時に関連資料として提示を求められることも想定されるため、業務の信頼性や説明責任の観点からも、削除せず体系的に保存しておくことが望ましいでしょう。
メール本文の保存範囲
見積書の内容がメールやSNSの本文に直接記載されている場合、その本文自体が「電子取引の情報を記録したデータ」とみなされ、電子帳簿保存法における保存義務の対象になります。そのため、メール本文を改ざん防止・検索性を確保した形で保存する必要があります。
一方で、本文とは別に見積書のPDF等が添付されており、そこに同一の取引情報が含まれている場合は、添付ファイルの保存のみで要件を満たすとされています。この場合、本文を保存しなくても問題ありません。
メールやSNSの本文が保存対象となる主なケース:
- 添付ファイルがなく、取引情報(取引日、金額、取引先など)が本文にのみ記載されている
- 本文にのみ証拠となる見積情報がある(例:LINEやチャットアプリでの見積送付)
複数受領時の対応
積書は取引先との交渉過程で金額や条件が修正・変更され、複数回発行されることが一般的です。電子帳簿保存法では、その中で「確定データ」となるものはすべて保存対象とされており、過去のバージョンも削除せず、適切に管理することが求められます。
ただし、単なる誤記訂正や日付修正など、軽微なミスによる差し替えについては、最終版のみの保存で差し支えないとされています。重要なのは、見積書の修正理由や発行経緯が明確になるように管理することです。
バージョン管理の具体例
- 見積番号やバージョン番号を付与して識別
- 修正履歴を残せるシステムや、発行日ベースのファイル名ルールを設定
- 最終版がどれか明確に分かるようフォルダ分けやフラグ付けを行う
まとめ

電子帳簿保存法により、見積書の保存にも法的な対応が求められる時代になりました。とくにメールやクラウドで授受された見積書は「電子取引」として扱われ、タイムスタンプや検索機能などの要件を満たした保存が義務づけられます。契約に至らなかった場合や修正があった場合でも、確定データとして保存すべきものがあります。実務に即した対応を整え、税務リスクを未然に防ぎましょう。
こうした課題を効率よく解決する手段としておすすめなのが、シヤチハタの「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」です。Shachihata Cloudは、電子契約と電子取引データの保存に対応しており、タイムスタンプ付与や検索機能など、電子帳簿保存法の要件を満たす機能をワンストップで提供します。無料トライアルも提供していますので、ぜひこの機会にお試しを。
資料請求はこちらから。
よくある質問
見積依頼書は電子保存できますか?
はい、見積依頼書も見積書と同様に、取引に関する情報を含む文書であれば電子帳簿保存法の対象となります。メールやクラウド経由で授受した場合は、要件を満たした電子保存が必要です。

 無料オンラインセミナー
無料オンラインセミナー 資料ダウンロード
資料ダウンロード Shachihata DXコラム
Shachihata DXコラム コミュニケーション
コミュニケーション ワークフロー
ワークフロー 文書管理
文書管理 セキュリティ
セキュリティ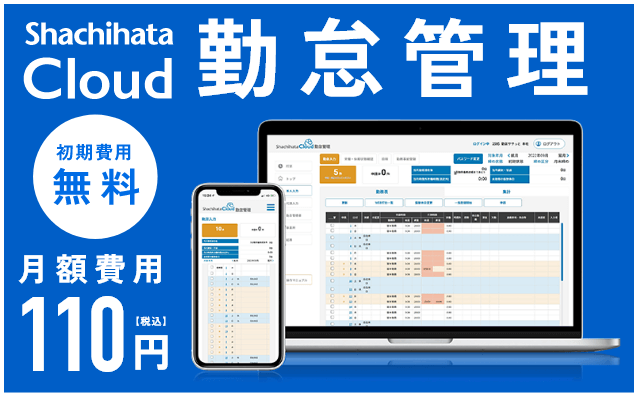
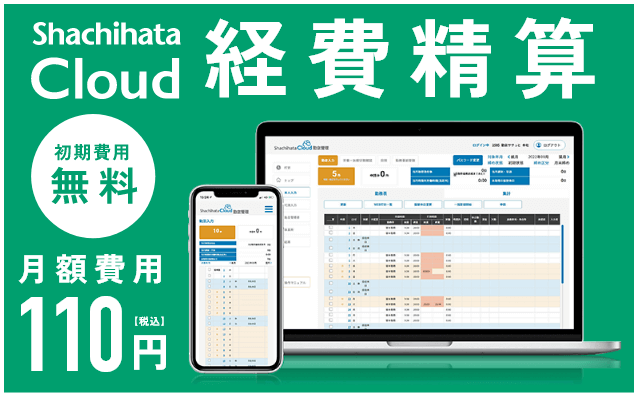

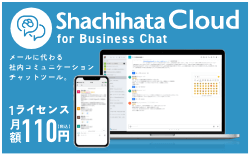
 シヤチハタ
シヤチハタ 乗り換え・併用を
乗り換え・併用を よくある質問
よくある質問 お悩み診断
お悩み診断 概算シミュレーター
概算シミュレーター オンライン相談
オンライン相談 ヘルプサイト
ヘルプサイト 障害に関しての
障害に関しての
 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら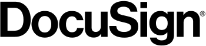 導入をお考えの方はこちら
導入をお考えの方はこちら



 PDF捺印ライブラリパーソナル
PDF捺印ライブラリパーソナル Shachihata Cloud
Shachihata Cloud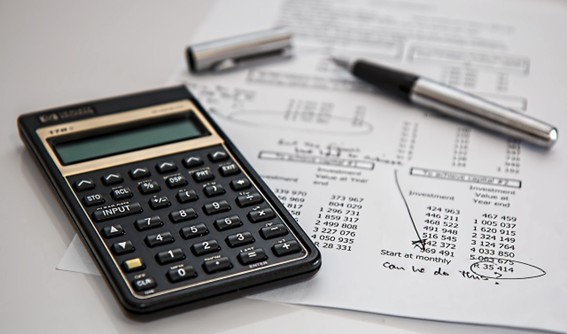








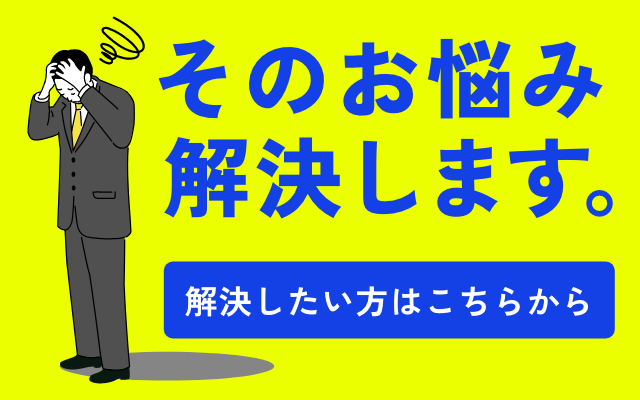

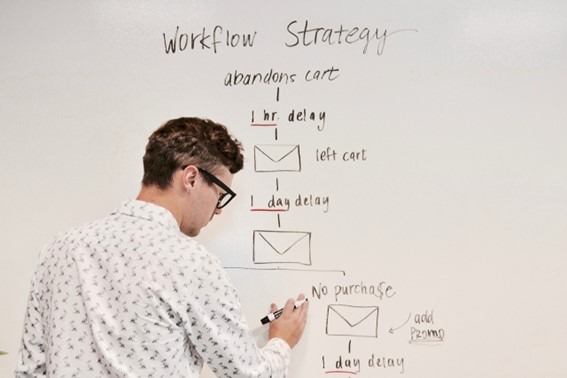

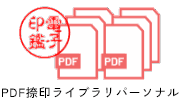
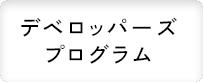



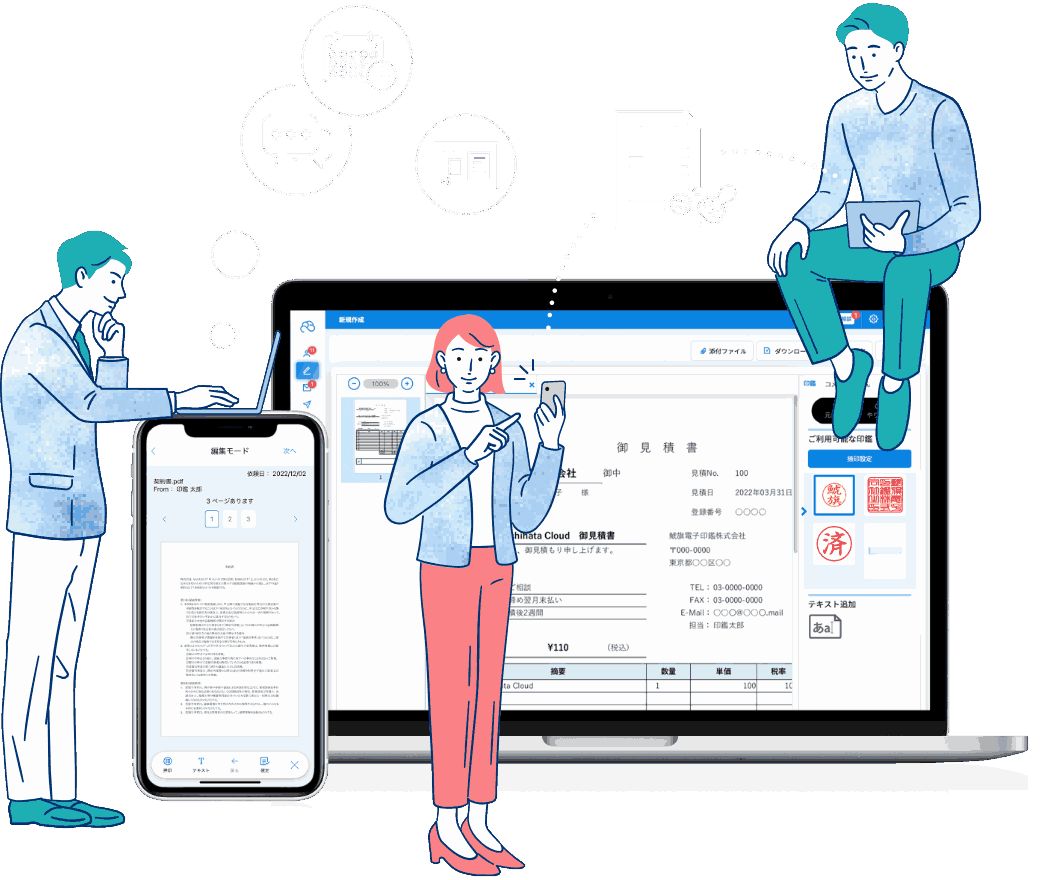

 Shachihata Cloud Channel
Shachihata Cloud Channel